【高温に伴う農作物等の管理対策の徹底をお願いします】
ページID : 14451
新潟地方気象台が7月10日に発表した1か月予報(7/12~8/11)では、
向こう1か月の気温は高いと予想され、さらに、14日発表の高温に関する早期天気情報
において、7月20日頃からかなりの高温になると予想されています(5日間平均気温平年差 +2.3℃)。
農作業時は気温の高い時間帯を避け、風通しの良い服装で、
こまめな休憩や水分・塩分の補給行って、熱中症を予防してください。
また、本年の気象は6月から高温と降水量が少ない状況が続いており、
一部のほ場では、土壌水分不足による生育停滞が生じています。
かん水により、土壌水分の確保と地温低下を図るなど、
下記を参考に農作物等の管理に十分留意してください。
高温に伴う農作物等の管理対策
【水稲】
- コシヒカリの分施体系
出穂期10日前頃:葉色が淡い場合は、2回目時期の穂肥を増量して確実に施用する。
出穂期6~3日前:葉色が淡い場合は、追加穂肥を検討し、穂が見え始めていても追加穂肥を施用する。
- コシヒカリの全量基肥体系
出穂期10日前以降:指標値より葉色が淡い、または、急激に低下している場合は追加穂肥を検討し、穂が見え始めていても追加穂肥を施用する。
- 水管理(出穂期前後)
土壌の乾燥がみられるほ場では速やかにかん水し、飽水管理を継続する。湛水ではなく、土壌が水を多く含んだ状態を維持する。
- 白穂や稔実障害、白未熟粒等の発生の防止
台風等の影響による乾燥した強風や極端な高温が予想される場合は、週間天気予報や番水計画を確認し、土壌が湿った状態を保てるように、早めにかん水する。ただし、高温時の長時間湛水は根腐れしやすいので、浅い湛水にする。
【大豆】
- 暗きょ栓の管理
1. 高温・少雨に備え、暗きょ栓は常時閉めておく。
2. 降雨により地下水位が急激に上昇した場合は、速やかに暗きょ栓を常時空ける。
3. 排水不良で常に地下水位の高いほ場は暗きょ栓を常時空ける。
- うね間かん水
1. 開花期以降に条間の土が白く乾き、朝や夕方に最頂葉中央の小葉の50%以上が反転した場合や、地下水位が地下60~70cmより低い場合は、うね間かん水を行う。
2. 1日以内に地表水を排水できるほ場でのみ行う。
3. 暗きょ栓は、かん水時は閉じて、終了後に開ける。
4. 高温時のかん水は根を傷めるので、朝夕の涼しい時間帯に行い、水が行きわたったら速やかに排水し、水の停滞による湿害を防止する。
5. 大区画ほ場では、水口側の湿害を防止するため、数日かけて明きょに水を回し、全体に水を浸透させてから、うね間かん水を行う。
- 病害虫防除
高温時はハダニ類に注意し、被害の拡大が懸念される場合は早めに防除を行う。
【園芸作物共通】
- かん水管理
かん水施設のあるほ場では、日中の暑い時間帯は避け、涼しい時間帯にかん水する。うね間かん水する場合、根腐れを避けるため長時間滞水させない。
- 病害虫防除
高温乾燥が続くとハダニ類、アザミウマ類やオオタバコガ等のチョウ目害虫、
うどんこ病の発生が多くなるため、適宜防除する。
日中高温時の薬剤散布は薬害が発生しやすいため、朝夕の涼しい時間帯に実施する。
- 施設園芸の温度管理
遮光・遮熱資材の利用や換気でハウス内温度を下げる。
遮光による収量・品質低下に注意し、天候に応じて光量を調整する。
- 夜間冷房の活用
ヒートポンプ空調機の設置されている施設では、冷房機能を利用して草丈の伸長や生理障害を抑制する。
ただし、収穫期の遅れや徒長により品質低下のリスクもあるため、使用は慎重に判断する。
【野菜】
- かん水等の土壌管理
1. 果菜類:地温上昇を抑制するために、厚めに敷きわらをする。定植する場合は白黒ダブルマルチ等を使用する。
2. 直は栽培(だいこん、にんじん等):発芽安定のため、発芽までスプリンクラーなどで1日数回かん水する。
- 育苗・定植
1. 苗床管理:寒冷紗等の遮光資材の利用および換気・通風で苗床温度の抑制。特に接ぎ木の養生管理では、外張およびトンネルを遮光し温度低下に努める。
2. かん水:苗の軟弱徒長防止のため、早朝を基本とする。日中高温時にしおれる場合は葉水を行う。また、晴天が続く場合は育苗後半の節水管理は軽めにする。
3. 定植作業:定食後の活着を図るため、夕方に実施する。定植する際、うね立て後の土壌が乾燥している場合は植え穴に十分かん水してから定植する。かん水が難しい場合は。定植直前に耕うん・うね立てする。
4. いちごの仮植床:黒寒冷紗で被覆し、活着するまで上から1日数回かん水し、葉を乾かさないようにする。
- 品目別の栽培管理
1. すいか:日焼け果防止のため、露出している果実はワラやつるなどで覆う。また、草勢が低下しないように定期的にかん水する。
2. 果菜類(ナス、ピーマン等):草勢低下防止のため、早期収穫に努める。また、下葉や弱小枝を除去し、通風と採光を図る。
3. トマト、ミニトマト:着色不良防止のためハウス屋根等に遮光・遮熱資材の展張や塗布を行う。
4. ねぎ:高温時の過度な土寄せは、生育停滞や軟腐病などの病害の発生原因となるので避ける。
5. えだまめ:収穫前追肥で草勢を維持し、乾燥が続く場合はうね間かん水を行う。
6. さといも、アスパラガス:かん水で生育停滞を防ぐ。
【野菜】
- 新梢管理
1. 過度な新梢管理は日焼けの原因になるため、通風採光や防除に支障ない範囲で行う。
2. にほんなし「新高」:高温・干ばつで果肉障害が発生しやすいことから、骨格枝基部の新梢管理に留めるなど、必要最低限とする。
3. ぶどう:急激な新梢管理により日焼け果が発生する場合があるため、葉数が少ない部位の果房には笠掛等により遮光する。
- かん水・下草管理
1. 干ばつが予想される場合は、土壌が乾ききる前に早めにかん水を始める。
2. 週間天気予報等を確認し、降雨の無い状態が続く場合は5~7日間隔で20~30mm程度のかん水を行う。
3. かん水用の水が十分確保できない場合は、樹幹下に溝や穴をあけ、効率良くかん水することで深層への水分供給を行う。
4. 草生法の園では、草刈りをすることで果樹と草の土壌水分の競合を避ける。清耕栽培では乾燥害を防ぐため、樹冠下部に敷きわらをする。
5. 幼木は根量が少なく乾燥に弱いので、優先的に敷きわらやかん水をする。
6. いちじくでのうね間かん水は、葉のしおれや葉焼けの状態を観察しながら、1週間間隔を目安に行う。
- 収穫
高温や乾燥が続くとナシやモモで水浸状果等生理障害が発生しやすくなるので、庭先選果を徹底し出荷果実への混入に十分注意する。
【花き】
- 球根類
1. チューリップ等の球根の貯蔵:通風に留意し、貯蔵庫内の温度をできるだけ下げる。また、過乾燥に注意する。
2. 促成切り花用のチューリップ球根:自然貯蔵では高温により花芽分化が遅延するため、冷蔵処理開始まで中温処理(20℃冷蔵庫内で管理)を行う。その際、エチレンガスによる障害発生を防止するため腐敗球の除去を徹底するとともに十分な換気を行う。
3. ユリの球根養生:強日射により上位葉に日焼け症状が発生し、球根肥大が抑制されることがあるため、地温が低い時間帯に定期的にかん水する。
- 切り花類、鉢物類
1. 生育初期:草丈やボリューム確保のため、十分にかん水する。
2. 出らい期以降:品質向上のため、必要以上のかん水を控え上位節間の徒長を抑える。
3. ユリ切り花の抑制栽培:草丈確保や奇形花発生防止のため、定植前の芽伸ばし・順化処理を適切に行う。また、定植前から遮光とかん水を行って地温低下と土壌水分を確保しておくとともに、定植後は十分なかん水と敷わらにより発根を促進する。
4. 露地切り花(キク・アスター等):日焼け防止や、葉温上昇の抑制を図るため、寒冷紗等の遮光・遮熱資材を利用する。
5. 切り花類の採花管理:朝夕の涼しい時間帯に採花を行う。採花後は、速やかに清潔な水で水あげを行う。また、採花時との温度差による花しみ等の生理障害発生を防ぐため、切り花貯蔵時の温度管理に留意する。
【家畜】
- 畜舎の管理
1. 断熱対策:屋根や壁に石灰や遮熱塗料等の塗布、屋根裏や壁・床への断熱材の設置、窓への寒冷紗の設置、窓への寒冷紗の設置、散水等を行う。
2. 通風確保:野生生物の侵入防止策を徹底しつつ、畜舎の開口部はできるだけ解放し、空気の流れを妨げないようにする。
3. 強制通風:大型ファン・送風ダクト等で強制通風する。
- 家畜の管理
1. 飼育密度を緩和し密飼いにしない。牛の場合は毛刈りも有効。
2. 大型ファン等の風が家畜に直接当たるよう、ファンの位置や角度を調整する。
3. 暑さが厳しい場合は、ホース又は細霧などによる牛・豚への直接散水等で体感温度を下げる。
4. 家畜の観察を励行し、急激な体調の変化が見られる場合は、速やかに獣医師の診療を受ける。
- 飼料の給与および飲水
1. 飼料給与は朝・晩の比較的涼しい時間帯に行い、また、1日に与える飼料の量を、多回数に小分けして給与し、急激な体温の上昇を防ぐ。
2. 消化の良い飼料及び粗飼料を給与する。カビの発生した飼料や品質の悪い飼料は給与しない。飼槽の残飼は変敗するのできれいに清掃する。
3. 常に新鮮で冷たい水が飲めるよう、ウォーターカップや水槽はこまめに清掃し、水量や水圧を確認する。
4. ビタミン剤及びミネラルなどを補給する。
【きのこ】
- ハウス内の高温による生育障害を防ぐため、空調設備のない施設は、換気等により適切な温度に管理する。
- 換気をする場合は、害菌・害虫の侵入防止対策を行う。
- 害菌の早期発見に努め、汚染された菌床は速やかに撤去する。
- 高温下では、きのこの品質低下が著しいので、適期に収穫する。
- 収穫したきのこは、速やかに保冷庫等で保管する。
- 露地栽培については、通風確保や散水などにより温度と湿度を管理する。
- 極端な温度変化による影響の早期発見に努め、適切に対応するよう留意する。
参考(新潟県および気象庁ホームページへのリンク)
【新潟県 高温に伴う農作物等の被害を防止するため、管理対策の徹底をお願いします。】
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/norin/250716kinkyu.html
【気象庁 北陸地方 早期天候情報】
https://www.data.jma.go.jp/cpd/souten/?reg_no=21
【気象庁 2週間気温予報】
https://www.data.jma.go.jp/cpd/twoweek/?fuk=54
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
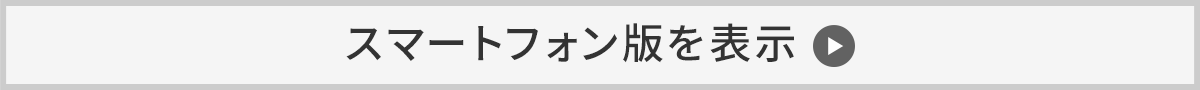












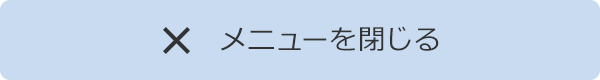





更新日:2025年07月18日