施政方針
令和7年度施政方針(令和7年2月26日議会定例会)
市長は、令和7年第2回阿賀野市議会定例会において、市政運営に対する基本姿勢や重点施策などを示す施政方針を述べました。
本日、令和7年第2回阿賀野市議会定例会におきまして、令和7年度の予算案、ならびに、関連議案のご審議をお願いするにあたり、市政に取り組む所信の一端を述べさせていただきます。
令和7年は、戦後80年、昭和の元号で100年、合併して20年が経過したことになります。先の当初予算説明会の折にも触れましたが、これまでの歩みを確認し、ようやく阿賀野バイパスが全線開通することを踏まえ、これからの阿賀野市を考え、様々な施策を「第3次阿賀野市総合計画」として、新たなスタートを切る年であります。
しかし、取り巻く環境を見渡すと、何気ない毎日が、いかに貴重か、身に染みて感じる出来事が世界各地で起きており、これが収まり、安寧な時が来ることを心から願うばかりであります。
また、我が国の政治、経済、金融等を取り巻く情勢は流動的であり、そして今、少子高齢化をはじめ家庭・地域集落構造の変化、経済や金融、物流、労働などを含む社会構造の変化を要因として、社会保険制度、社会保障制度、医療制度、教育制度の在り方をどうするのか、その検討が喫緊の課題となっており、将来に対する不安も解消されていない状況にあります。
この様な中、人口減少の流れに抗うことが難しいことを認識し、その上で何を成すか考え、限られた人材と財源の中で、最も有効な手立てをもって、次の世代へどのようにつなげていくか、常に最適解を求めていく姿勢が大切でると認識しています。
加えて、地域の持つ潜在能力を引き出し、阿賀野市の魅力と合わせ、新たな「ヒト、モノ、コトの流れを生み出していこう」というアクティブな気持ち、自己解決を図ろうとする意識の醸成が必要であると考えており、市民の皆さま、自治会などとの連携強化を通じ、このことに努めてまいります。
特に、人口減少下では、官民が一体となり、単に知識や能力があるだけではなく、歴史や文化を大切にする人材や人を思いやる人材、阿賀野市にとって不足している人材の育成に取り組むことが、未来の阿賀野市のためにも有効であり、Uターン奨学生への奨学金返済支援の復活強化をはじめ、医療的ケア児保育支援、ひとり親家庭子ども学習支援、私立認定こども園の改修費補助など、子育て環境の整備を進めてまいります。
更に、教育環境では、京ヶ瀬中学校グラウンドの整備や市内小学校のプールの再編整備を進め充実を図ってまいります。
さて、本市には、1,700を超える優良・有望な企業が存在し、地域の雇用や経済を支えていただいておりますが、国内には、従業員2,000人以下の中堅企業が約9,000社あり、中小企業を含めますと120万社以上の企業があります。その多くの企業から、本市に関心を持っていただき、そして立地につながるよう、引き続き企業誘致を推進するとともに、関係機関・組織と協議を行いつつ、新技術・環境技術を支援し、サステナブルで確実な成長につながるよう、フォローアップに努めてまいります。また、市内企業と市内就業希望者のマッチングを通じ、人材が確保できるよう環境の整備を行い、合わせて地域おこし協力隊や専門的知識を有する人材を活用し、農業や観光、デジタル分野などの担い手の育成を進め、地域の活性化と市民サービスの向上を図ってまいります。
地場産業の安田瓦につきましては、近年、瓦ロード周辺の整備が進み、交流人口拡大のための拠点の一つとなっており、加えて、「北限の瓦づくり」としての文化的評価の向上も目指しながら、普及のための支援を拡充いたします。
待望の阿賀野バイパス全線開通をチャンスと捉え、観光の振興と交流の推進を体系立てて取り組むとともに、ふるさと寄附金を活用した、瓢湖水きん公園など観光施設の整備による集客力の向上と合わせ、市内観光の利便性向上と活性化による観光事業者への支援を展開してまいります。また、このことは、阿賀野市の地政学的位置付けを自ら理解した上での取り組みが大切であり、暮らしやすいまちづくりにおいても、重要な要素であると考えております。
そして、暮らしやすいまちづくりの重要な要素の一つに、安心して医療を受けられる体制の維持がありますが、人口減少や薬価等診療報酬の改定などの影響により、医療・病院運営が困難な状況となっており、現在、これからの医療体制についての議論が進められています。
私たちも医療を受ける側としてどうであったか、また、これからどうあるべきか考えていく必要があり、それぞれの役割を果たしていくことが求められております。
市としては、県、ならびに、厚生連との情報共有や人的つながりを活用しつつ、医療資源の確保、また、将来を見越し、デジタル技術を活用したオンライン診療などの可能性について、検討を進めてまります。
議員各位におかれましては、従前より願っておりますが、医師の確保に更なるお力添えをいただけますよう、あらためてお願いを申し上げる次第であります。加えて、多額の費用を必要とする、あがの市民病院の医療機器の更新は、今後も継続的に発生する見込みでありますが、それに見合う基金残高が少なく、一般財源からの繰り入れが想定されます。このことにつきましては、あらゆる方策を検討し、対処してまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
また、予防医療の観点や医療現場がひっ迫しないよう医療負担の軽減を図る上でワクチン接種は大切であります。市では、引き続き、中学生以下のインフルエンザ予防接種費用の助成を行うとともに、国の方針に基づき、全体的に免疫力が低下する高齢者の皆さまを対象とした、帯状疱疹ワクチン接種、新型コロナウイルスワクチン接種に係る費用を計上するほか、子宮頸がん予防のためのHPVワクチンのキャッチアップ接種についても、その費用を計上いたします。
そして、年々増加している空き家でありますが、暮らしやすいまちづくりのために、その解消に向けた取り組みや施策の実行が待たれております。市としましては、それらを実行することによって、防災や防犯などの安全面や衛生面をはじめとする生活環境、都市環境の整備が図られることから、空き家の除却に対する支援を行うこととしております。
さて、言うまでもなく、本市の生産基盤は稲作であります。近年は、その生産基盤を脅かす天候の異変、加えて、人、家畜・家きんを問わず様々な感染症が発生し、生活環境の著しい変化を実感せざるを得ない状況となっています。大量廃棄など、地球の生態系の循環能力を超えた人間の行動により「地球丸」がきしみ始めているのかもしれません。D.モンゴメリーとA.ビクレーが書いた「土と脂」では、健康に生きるために必要な食の在り方を取り上げ、土壌の重要性にかかる研究結果を例に引き、健康な作物の生育には土壌微生物が必須であり、人間の健康は健康な作物に、健康な作物は健康な土によることを示し、「土、地球、人間自身のために環境の回復の道を選ぶなら、まだ間に合う」と、土づくりの農業、環境再生型農業の重要性を説いています。
また、国際有機農業連盟は、「有機農業は伝統、革新、科学を組み合わせて人間にも環境にも利益をもたらし、関与する生物と人間の公正な関係を築き、生活の質を高めます」と謳われており、必要な食料を作るために、生活基盤である生態系を破壊しては、生きる場所がなくなる、という意思が読み取れます。我が国が瑞穂の国と言われ、更に稲作と牛が密接な連携によるものであることを考えれば、幸いにも本市には、その基盤が備わっていると言えます。
地域の生態系の循環に順応し、畜産の面からの「牛づくり、草づくり、土づくり」は、正に「コメ作り」に通じるものであり、本市の生産基盤環境に合致していることから、関係者や関係機関、関係団体とともに、有機農業・オーガニック農業の推進を加速化してまいります。
一方、これら多岐にわたる施策、事業を実施する中で、市が保有する公共施設について、これまで施設修繕など、実施を先送りしてきた事項が数多く残っており、町村合併以降、手付かずの案件として残っていることは、誰もが承知していることであります。建設から相当の年数が経ち、昨年あたりから次々に、施設の利用に一部不都合が生じております。次の世代のためにも、「やるべきことは、やる」ことが求められております。これらの負託に応えるためにも、人口減少のダメージをいかに少なくするかを意識しつつ、縮小社会適応策を展開していくスタートの年でもあります。市民の皆さまや将来世代に負担を強いることにならないためにも、対応策におけるダウンサイジングを新たな創造の結節点として位置付け、事業の組み合わせにより新しい強みを生み出せるよう心掛け、施設保有量の適正化を進めるとともに、維持管理の適正化、施設運営の適正化に取り組んでまいります。
そうでなければ、結果的に市民の皆さまや将来世代に負担を強いることになります。議員各位からのご理解をいただきながら対処してまいりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
そして、同時に先程申しあげた「牛づくり、草づくり、土づくり、コメづくり」に加えて、もう一つ大きなポイントがあります。
それは、「人づくり」であります。人口の減少、言い換えれば労働人口の減少においては、業務プロセス全体の点検と見直しを図り、データの利活用により新たな価値を創出することが求められています。
私たちを取り巻く情勢は、刻一刻と変化しております。国、県が示す方向を確認しながら、本市の取り組みも柔軟にカスタマイズしなければなりません。「今までこうであったから、これからもこうでいい」という意識を一度脇に置き、物事を、少し角度を変えて見てみる、そして見たことをしっかりと見極め、行動に移せる人材、また、課題はテーマ毎にカンファレンスを行い、何故このようことに至ったか、至るまでの経過を確認し、きちんとした診断と、その後の対処方針が決められる人材の育成と確保に努めてまいります。むろん、このことに関しましては、人的資本を弱めたり壊したりすると、組織の持続可能性も壊すことになることを自覚し、取り組んでまいります。
一方、職員にとって、職員としての行動規範はとても大切であります。
「社会のためになるか「市民のためになるか」「組織・職員のためになるか」という行動規範と「公平」「公益」を矜持とし、ラグビー競技で言われている「品位・情熱・結束・規律・尊重・貢献・寛容・探求」という言葉をもって「ワンチーム」として、そして三つのS、「Strong強く」「Spread広く」「Social社会とのつながり」、この三つのSを意識して職務にあたることを期待しているところです。
現在も、職場環境の改善を求め、職員の意見、諫言を聞きながら取り組んでおりますが、市民の皆さまから「これまでより職員の表情が明るくなった」という声をお聞きしております。来庁される市民の皆さま、加えて、市外からお越しの皆さまからも、明るい気持ちになったと言われるような、ウェルビーイングが感じられるように、またオフィスエンゲージメントを高めて集まりたくなるような、成長につながるような市役所を、リーダーシップより、フォロワーシップをもって作ってまいります。こちらにつきましても、議員各位からの一層のご理解とご協力をお願いする次第であります。
結びに、令和7年度当初予算ならびに政策・事業につきましては、先に申し上げましたとおり、「第3次阿賀野市総合計画」において、新たに策定する6つの分野b津政策、および、総合的政策に基づき取り組むものであります。まちづくりの目標である、「住みよい、いきいき元気なまち」の実現に向けて、「みんなで創る阿賀野市」の理念のもと、「人がつながることで、環となり、今をつなげることで、未来につなぐことができる」という思いを込め、職員とともに「ワンチーム」となり、前に進めてまいります。
議員各位におかれましては、重ねてのご理解を衷心よりお願い申しあげ、私の施政方針といたします。
阿賀野市長 加藤 博幸
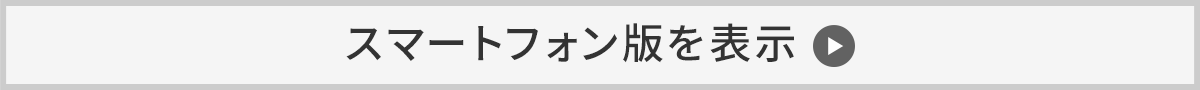












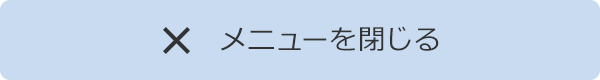





更新日:2025年04月01日