介護保険料の決め方、納付方法
保険料は、万一介護が必要となったときのために、そしてみんなで介護を支えるために、40歳以上の全員が納めることになっています。
65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2通りの納め方があります。ただし、介護保険法第135条の規定に基づき、特別徴収が原則となります。本人の希望により徴収方法の選択はできません。
特別徴収(年金からの天引き)
年金からの天引きで保険料を納める方法です。偶数月において、年6回支払われる年金から介護保険料を納付いただきます。
年6回の内、3回(4、6、8月)に関しては、市民税が確定する前のため、年間保険料が算出できないことから、前年度の2月と同額を仮徴収します。ただし、徴収期間中に所得段階の月額と1期分の保険料額の差額が大きい人などは、6、8月の2回分で保険料を平準化する場合があるため、前年度の2月と保険料額が異なることがあります。
10月分以降に関しては、確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いた残りの額を3回(10、12、2月)に分けて納付いただきます。
|
仮徴収 |
本徴収 |
||||
| 4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) | 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
|
当年度の市民税が確定するまでの3回を仮徴収といいます。 仮徴収期間は、前年度の2月(6期)と同額を納めていただきます。 ただし、所得段階の月額と1期分の保険料額の差額が大きい人などは、6月(2期)、8月(3期)保険料を平準化している場合があります。 |
前年の所得などに応じて年間の保険料額を決定します。 確定した年間の保険料額から仮徴収期間(4、6、8月)の納付額を差し引いた残りの額を3回で納めていただきます。 |
||||
1種類の年金で年額18万円以上受給されている方につきましては特別徴収の対象となります。(老齢福祉年金を除く)
ただし、以下の要件に該当する方は一時的に普通徴収で納めていただきます。
- 年金を担保にして融資を受けられている方
- 保険料が減額となった方
- 年度の途中で65歳になった方
- 年度の途中で他市町村から阿賀野市に転入した方
(注1) 上記の要件の他にも、一時的に普通徴収で納めていただく場合があります。
(注2) 年金保険者(年金機構や共済組合)との調整が完了しましたら、特別徴収が開始されます。(特別徴収の開始のお手続きは必要ありません。)調整が完了するまでの間は普通徴収で納付いただきます。
普通徴収(納付書または口座振替)
納付書または口座振替で保険料を納める方法です。年間保険料を4月から翌年の3月までの12回に分けて納付いただきます。
年12回の内、3回(4、5、6月)に関しては、市民税が確定する前のため、年間保険料が算出できないことから、前年度の所得段階で算出した保険料額を仮徴収します。7月以降に関しては、確定した今年度の保険料段階の年間保険料から仮徴収分を差し引いた残りの額を9回(7~翌年3月)に分けて納付いただきます。
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||||||||
| 4月 (1期) |
5月 (2期) |
6月 (3期) |
7月 (4期) |
8月 (5期) |
9月 (6期) |
10月 (7期) |
11月 (8期) |
12月 (9期) |
1月 (10期) |
2月 (11期) |
3月 (12期) |
|
今年度分の市民税が確定するまでの3回を仮徴収といいます。 仮徴収期間は、前年度の所得段階で算出した保険料を納めていただきます。 |
今年度の基準額に基づき、前年の所得などに応じて年間の介護保険料額を決定します。 仮徴収期間の納付額を差し引いた残りの額を9回で納めていただきます。 年度途中で特別徴収(年金からの天引き)に切り替わる場合は、特別徴収開始の約2か月前に通知書を送付します。 |
||||||||||
受給している年金の年額が18万円未満の方や年金を受給していない方につきましては普通徴収の対象となります。
普通徴収の納期限日は毎月の末日です。月の末日が休日等の場合、次の直近の営業日です。ただし、12月のみ月末ではなく25日です。25日が休日の場合、直近の営業日となります。
納付書
納付書で納める場合は以下の場所で納付いただけます。
- 阿賀野市役所、阿賀野市役所各支所
- 第四北越銀行、大光銀行、はばたき信用組合、加茂信用金庫、新潟かがやき農業協同組合、新潟労働金庫、ゆうちょ銀行または郵便局(新潟県・長野県のみ)
- 納付書に記載のあるコンビニエンスストア
- スマートフォンアプリ(PayPay d払い au Pay)
(注1)コンビニエンスストアやスマートフォンアプリでは、納期限が過ぎた納付書は納付できません。
(注2)LINE Payでの納付につきましては、令和7年4月24日からご利用できません。
口座振替
口座からの引き落とし日は、普通徴収の納期限日となります。引落日に残高不足などの理由により引き落としができなかった場合は、15日が再振替日となります。15日が休日等の場合は次に直近の営業日となります。
口座振替をご希望の方は、阿賀野市役所介護保険係までご連絡いただき、後日郵送にて届く口座振替申請書をご返送いただくか、阿賀野市役所介護保険係又は各支所、市内金融機関窓口にて直接申込手続きをしてください。手続きには通帳と通帳にご利用の印鑑が必要となります。
(注)口座振替の開始は、通常、申込日の翌月からになります。
阿賀野市の介護保険料所得段階一覧表
(阿賀野市基準額83,100円(年額)…保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに見直されます。)
|
所得段階 |
対象者 |
第9期調整率 |
第9期保険料(円) 年額 |
|---|---|---|---|
|
第1段階 |
|
基準額の28.5% |
23,700 |
|
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円超120万円以下の方 |
基準額の48.5% |
40,300 |
|
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
基準額の68.5% |
56,900 |
|
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 |
基準額の90% |
74,700 |
|
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円超の方 |
基準額 |
83,100 |
|
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額の120% |
99,700 |
|
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上160万円未満の方 |
基準額の130% |
108,000 |
|
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が160万円以上210万円未満の方 |
基準額の140% |
116,300 |
|
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上260万円未満の方 |
基準額の150% |
124,600 |
|
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が260万円以上320万円未満の方 |
基準額の160% |
132,900 |
|
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額の170% |
141,200 |
|
第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額の190% |
157,800 |
|
第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額の210% |
174,500 |
|
第14段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額の230% |
191,100 |
|
第15段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額の240% |
199,400 |
(注1) 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前または大正5年4月1日以前に生まれた人で、一定の要件を満たしている人が受けている年金です。
(注2) 合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した金額のことです。所得段階が1~5段階の人の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。また、分離譲渡所得がある人の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
(注3) 令和7年4月1日から介護保険法施行令が一部改正されることに伴い、介護保険料所得段階の所得基準額の一部について、80万円から80.9万円に見直されました。
40~64歳の方の保険料(第2号被保険者)
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料は、医療保険料(医療保険税)に上乗せした形で納付いただきます。なお、保険料の算定方法に関しては加入している医療保険で異なります。算定方法や納付方法などの詳細に関しては加入している医療保険にお問い合わせください。
(注)40歳から64歳までの被扶養者の方は個別に保険料を納める必要はありません(加入する健康保険の被保険者全体で負担することとなります)。
国民健康保険に加入している方
医療分と介護分を合わせて、1つの国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。保険料の計算方法に関しては、所得などに応じて決定されます。
職場の健康保険に加入している方
医療分と介護分を合わせて、1つの健康保険料として、給料から差し引かれます。計算方法は加入している医療保険の算定方法によって決まります。(原則として本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担します)。
保険料の滞納
滞納が続くと、サービス利用のとき、いったん費用を全額負担し、あとから払い戻される「償還払い」になったり、保険給付の一部または全部を差し止められることなどがあります。
保険料が減免
災害などで、一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。
高齢福祉課介護保険係にご相談ください。
保険料と公費の割合
保険料50%
- 第1号被保険者(65歳以上)の保険料 23%
- 第2号被保険者(40~64歳以下)の保険料 27%
公費50%
在宅介護分
- 市町村の負担金 12.5%
- 都道府県の負担金 12.5%
- 国の負担金 25%
施設介護分
- 市町村の負担金 12.5%
- 都道府県の負担金 17.5%
- 国の負担金 20%
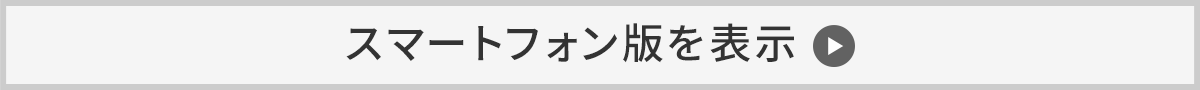












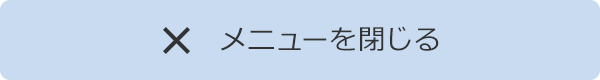





更新日:2025年04月24日